
あなたは個人的には傷害保険に入っていると思いますが、パークゴルフサークルの団体ではどうでしょうか。
特にこれから同行の士を集めて、サークルやクラブを作る予定のある方は是非考慮しておいた方がよろしいですよ。
万が一に備える
保険の目的から言えば、当然「万が一に備える」ということですよね。
あって欲しくはありませんが、自分達が主催した大会や例会で事故や負傷者が出たりするのは困ります。
もちろん、金銭のみで片付く問題だけではありませんが、入院や治療を行えば、余分な出費を余儀なくされることになります。
そんな時に、当人にそういう負担をかけないのも主催者側の配慮というものではないでしょうか。
安い費用
団体での傷害保険の費用は安いものです。
私たちのサークルで加入している保険は40名で年間5.940円です。
これは前年度の大会・例会参加者の延べ人数で決まります。私たちの場合、延べ人数が660名でこの金額です。
1大会・例会あたり、一人9円です。
これは参加のために、家を出てから、帰宅するまでのすべての行程が対象となっています。

その間の事故すべてが対象となる訳です。ですから、皆さんで遠征したり、泊を伴うような行事についても有効な訳です。
幸い、今年一年はコロナの影響で回数が少なかったせいもあり、適用するような事故はありませんでした。
しかし、何が起こるか分からないのが人生です。
明日が読めない
一昨年度は、メンバーの一人が第2打地点に歩いている時に、次のホールでティーショットした人のボールが木に当たり、跳ね返ってそのメンバーの額を直撃しました。

幸い命に別状はありませんでしたが、内出血をして翌日は目の縁が青く変色していました。
ご当人はしばらくサングラスが外せなくなりました。
こんなことがあってはいけませんが、そういう事故は起こらないとは言えません。実際に死亡事故も起こっています。
それはまだ全員ティーショットを打ち終えていないのに、一人だけ自分の打ったボールの方に歩いて行きました。そこに後の人のティーショットしたボールが顔に直撃したという事故です。
全員がティーショットを打ち終わるまで、ティーグラウンド横で待つことはマナーだけでなく、事故を防ぐという意味もあります。
守ろうマナー
長い間パークゴルフを楽しんでいるプレイヤーは十分過ぎるほど理解をしていますが、初心者のプレイヤーで時折見かけられる場面があります。
その多くが家族でのプレースタイルです。特にお子さんは自分のボールのある場所に行きたがるようです。だからまだ全員打ち終わっていないのに、待ちきれなくて急いでいくことがあるのです。
そういう場面を見た時、私は必ず声をかけるようにしています。それは一緒に回っているお父さんやお母さんが気を付けてあげないといけないことです。

ルールやマナーの問題とは違って、安全にかかわることは絶対に守っていただきたいことですから、その場でお伝えしていますが、今でも時折そういう組を目にすることがあります。
初心者は受付の人にもすぐにわかることですが、受付でそのような安全にかかわる注意はしてはくれません。
コースによってはプレイ中の安全について、パンフレットやスコアカードに記載していることもありますが、果たしてそれらの人たちはそこまで目を通してくれるでしょうか。
受付では初心者の組が申し込みにきたら、最低でも「全員がティーショットを終えるまで、前に出てはいけません」ということを伝えて欲しいと、個人的には思います。
最初のうちは、ルールを知るよりは、楽しくプレイすることでパークゴルフの楽しさを知ってもらうことの方が良いとは思いますが、安全に関しては徹底してもらいたいと感じております。
公益社団法人日本パークゴルフ協会
パークゴルフの総元締めである「公益社団法人日本パークゴルフ協会」では危険を防ぐために、次のように呼びかけています。
第2打以降は、ホールカップに遠い人から順に打ちます。声をかけあって危険のないようにし、他のメンバーは打ち終わるまで、後ろにさがって静かに待ちましょう。
プレーヤーは、常に前後左右の安全を確認するのがエチケット。他のメンバーは打つ人の前に立ったり、アドレスしたときに動いたり、声を出したりしないのがエチケットです。
OB(アウトオブバウンズ=プレーが禁止されています。)の近くに転がったボールのゆくえが心配でも、他のメンバーのスイング(クラブを振ってボールを打つ=ストローク)が終わるまで待ちましょう。
手元が狂うということもあります。万が一、前方や隣りのコースのプレーヤーやギャラリー(観客席)のほうにボールが飛んでしまったときは、すぐに「フォアー」と声をかけて、危険を知らせましょう。

まだ加入されていないグループや団体は、是非パークゴルフ保険に加入されることをお勧めいたします。公認のサークルは保険加入が義務となっているはずです。

是非ご一考ください


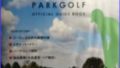

コメント